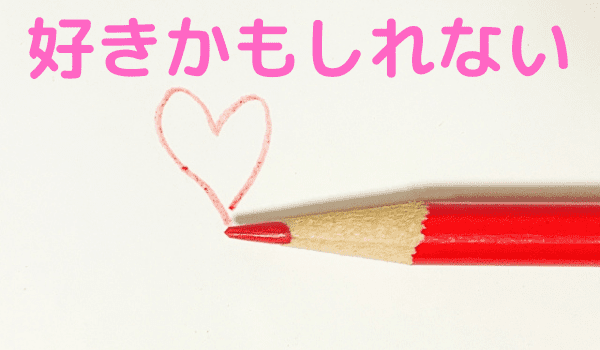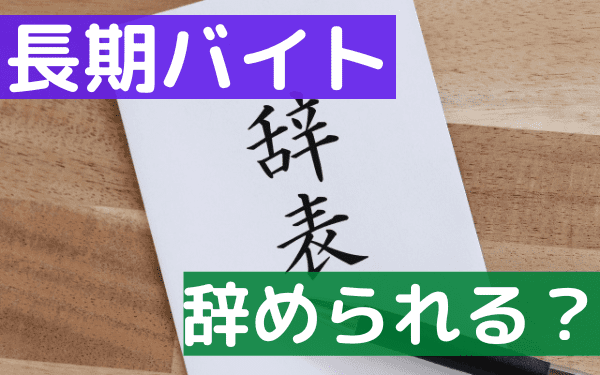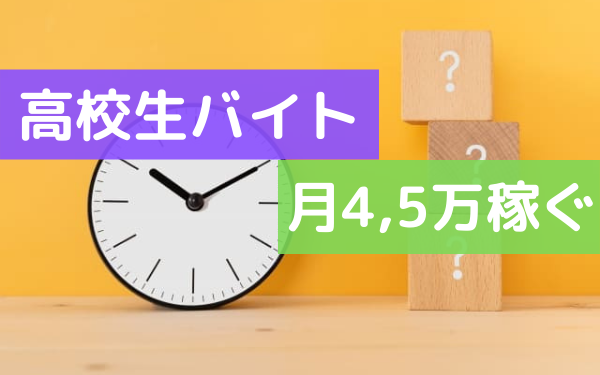バイトを休みすぎると判断されると大学生は危険です。
怒られたり職場で孤立して気まずかったり、最悪クビになる可能性もあるんですね。
そうならないために、上手な休み方を見ていきましょう。
バイトを休むときは頻度より、理由やタイミングの方が重要だったりします。
職場に迷惑をかけない範囲内で、授業やプライベートとアルバイトを両立することを意識すると良いですよ。
バイトを休みすぎの大学生はヤバい?基準は”頻度”より”負担”
まずはバイトを休みすぎと判断される基準について見ていきます。
学生の場合は学業やプライベートな予定などで、休みが必要なのは職場も理解しているはず。
でも休む回数や、休み方に問題があると、周囲からの評価は下がってしまうんですね。
① バイトを休みすぎと思われる基準はどれくらい?シフト周期に注目
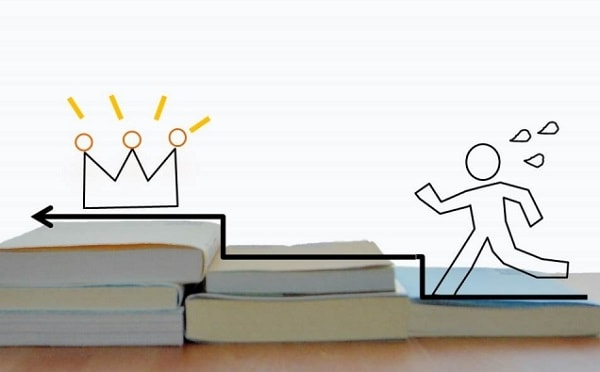
具体的に『1ヶ月で○回休んだら休みすぎ』という基準はありません。
職場で印象に残った時点で、『あの子は休みすぎている』と判断されます。
ではどんな休み方をしていると印象に残りやすいのか。
それはシフトを守れているかです。
シフトが1ヶ月単位であれば、毎月のように急な休みをもらっていると”休みすぎ”と判断されます。
事前に作ったシフトを、いくら守れているかが1つ目のポイント。
逆にシフトを守ることが多ければ、多少はバイトを休むことはあっても問題ありません。
体調不良や急な予定で、バイトを休むことは誰だってあります。
② バイトを休む理由が個人的すぎるとヤバい!体調不良なら問題ない

職場の従業員が納得できる休暇理由であるかも、あなたの印象と関係してきます。
例えば体調不良や法事などであれば、当日欠勤はやむを得ませんよね。
こういった急なトラブルには、スタッフ同士で協力していくのが理想です。
ただ急な休みの理由が、個人的なものだったらどうでしょうか?
職場での不満は溜まりやすいと言えます。
- テスト勉強をしたい
- 友達から遊びに誘われた
- 何となくやる気が出ない
自己管理の甘さからくる休暇は、職場の人がイラッとしやすいです。
プライベートな予定を入れるよきは、シフト申告時に空けておくのが理想。
シフト申告時であれば休む理由も不要で、特定の日にお休みをもらいやすいです。
シフト作成後の変更であれば、職場の人が理解できるような理由であるかが重要となります。
③ バイトを立て続けに休んだり直前や当日欠勤が多いとウザい

バイトを休むときはタイミングも重要になってきます。
理想的なタイミングはシフト申告時。
店長に『○月○日はお休みが欲しいです』と伝えれば問題ありません。
シフト自体が減っていなければ、バイト先から不満が出ることもないでしょう。
逆にできるだけ減らしたいのが、直前の休暇や当日欠勤となります。
もちろん体調不良や家庭の事情であれば仕方がない部分もあります。
ただそういった理由は頻度が少ないはずなので、何度も当日欠勤するのは問題行為。
バイト先の人も”また休み?”と、あなたに悪い印象を持つキッカケとなります。
大学生であれば学業やサークルなどと両立できるシフトを組みましょう。
参考⇒大学生がバイトするときのシフトの組み方は?理想の入れ方
- 作成したシフトを守れないことが多い
- 休む理由が個人的なものが多い
- 直前の休暇や当日欠勤が多い
バイトを休みすぎると大学生はどうなる?
バイトを休むときは頻度ではなく、迷惑をかける休み方の方が印象を持たれるという話でした。
では実際にバイトを休みすぎると大学生は、どういった対応を取られるのでしょうか?
すでに今の職場で同じような状況であれば危険サインと言えます。
① 店長に怒られたりシフトカットされたら信用が下がった証拠

何度も休むと店長や社員さんから注意を受けることになります。
『休みすぎだ』と怒られたり、『今度からは守れるシフト表で提出しなさい』など。
あなたが休むたびに、店長は代わりの人に連絡したり自分が残業する必要が出てきます。
そういった職場への負担を無くすために、あなたを怒るのは自然な流れと言えるでしょう。
そういった注意を続けても、あなたが休み続けるなら、シフトカットをされるかもしれません。
希望するシフトが通らず、全然働かせてもらえなくなるんですね。
急に休んで職場を混乱させるスタッフの希望シフトを聞く必要も、店長からしたらありません。
シフトカットまでいくと信用度はすごい下がったと考えて良いでしょう。
辞めることも視野に入れて、今後の働き方を改善する必要が出てきます。
② 休みすぎると不満や反感が積もってバイト先で孤立しやすい

休みが多いと周囲から判断されると、従業員同士の距離感が変わります。
好意的でなくなったり、会話が続かなくなったり。
次第に不満が溜まっていくと、無視されて孤立する危険も出てきます。
バイト先で孤立すると一気に働きにくくなるんですね。
バイトを辞めるか、時間帯を変えて一緒に働くスタッフを変えることも検討しましょう。
心を入れ替えて一生懸命に働いても、信頼を取り戻すのは時間がかかります。
③ 休みすぎる状況が続けばクビを言い渡されるかも

怒られたり注意を受けても勤務態度が変わらなかった。
そうなると店長としても最後の手段をとるかもしれません。
それがクビを勧告すること。
勤務態度に問題があれば、雇い主はアルバイトをクビにすることができます。
次のアルバイト先で、『前のバイトは何で辞めたの?』と聞かれたら正直に答えづらくなりますよね。
なのでクビを言われることだけは避けましょう。
その前にアルバイトを辞めて、もっと大学生活と両立しやすいバイトを選ぶ。
もしくは就活が近づいているなら、いったんアルバイトを中断することも検討した方がいいです。
参考⇒大学生はバイトをいつまで続ける?就活シーズンが辞める時期
- 店長に注意されたり怒られる
- 職場で孤立したり気まずくなる
- 勤務態度を改めなければクビになることも
バイトを休みすぎて気まずい!申し訳ないという罪悪感の薄め方
休みすぎたことを反省し、現状を変えたいなら、次の3つを意識しましょう。
上手な休暇の取り方や、潔く辞める判断も必要になってきます。
① 今後バイトを休みたいときは早めに伝える!理想はシフト申請前

今までどういったときに休んでいたか、その共通点を思い出してみましょう。
そうするとシフトを工夫すれば、急に休みを申請する必要が無くなってきます。
⇒月曜はアルバイトをいれない
⇒事前にテスト前はシフトを入れない
⇒金曜はシフトを入れない
このように過去どういったときにバイトを休んでいたか。
そこに共通点があれば、シフト申告時にそういった曜日を避けることができますよね。
こうすれば急に予定が入ってもバイトを休まずに済むようになります。
次回以降のシフトを組むときに、以前と同じようにシフトを作ってはダメ。
休む原因を突き止め、少しでも休む頻度を減らせるようなシフトを考えてみましょう。
参考⇒大学生がバイトで週3~週4がきついとき!お店に相談するコツ
② バイトを休むのではなく誰かとシフトを交換するという方法もある

どうしてもバイトを休みたいときは、休み方を工夫するという方法があります。
それが休暇ではなくシフト交換をお願いするという方法。
例えば誰か仲の良いスタッフに、シフトを交換できないか相談します。
こうすればバイトを休むのではなく、シフトを交換しただけなので、職場への負担は軽くて済みますよね。
店長もスタッフ同士でシフトを交換したのであれば、シフト調整など手間が増えることもありません。
職場で助け合えるような関係性のスタッフがいれば、シフト交換できないか提案してみましょう。
もちろん相手が困っているときは、あなたが積極的にシフトを代わってあげるのも忘れずに。
③ 今後も休みたい日が続くのであればバイトを辞める勇気も必要
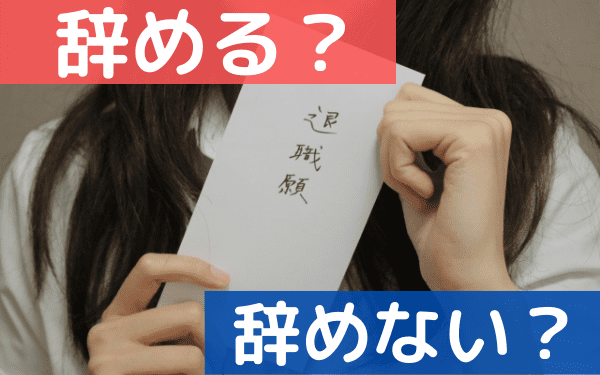
体調不良だったり嫌な上司がいる場合など、バイトを休みたくなる原因を自力で取り除けないこともあります。
その場合は今のアルバイト先を辞めるという選択肢も考えた方がいいです。
無理に続けても、また急に休めば職場の人に迷惑をかけてしまいますよね。
そうなれば今以上に罪悪感を感じたり、申し訳ない気持ちでいっぱいになります。
アルバイトをしていても楽しめないし、あなたもお店側にもメリットは薄いでしょう。
こうなるとあなたがアルバイトを辞めて、もっと働きやすいバイトを選んだ方が良いと判断できます。
例えば短期バイトであれば、契約期間が短いので集中して働きやすい。
夏休みや冬休みなど授業やサークル活動がない曜日を選べば、両立も簡単になります。
このようにもっとあなたに向いているアルバイトが他にあるかもしれません。
もし辞めるのが抵抗があるなら、以下の記事も参考にしてください。
- 休む原因を突き止めた上でシフトを組む
- 仲がいいスタッフにシフト交換できないか相談する
- もっとマイペースに働けるアルバイトに変える
バイトを休みすぎると職場で信用がなくなる!まずは次回以降のシフトを工夫しよう
バイトを休みすぎると”百害あって一利なし”の状態になります。
スタッフや店長から不満が生まれるし、あなた自身も職場にいづらくなります。
もしそんな状況を改善したいなら、できるだけ休まずにすむシフトを考えましょう。
少しシフト自体を減らしてプライベートを優先するのもありです。
シフトを組んでから休暇を申し出るより、最初から無理なく続けられるシフトを申請した方がいいので。
対処しても状況が改善しないなら、もっと働きやすいバイトに変えた方がいいかもしれません。
家から近かったり、在宅ワークなど続けやすいと感じるバイトには個人差があります。
無理に今のバイトを続けても、お互いにメリットはありませんよ。